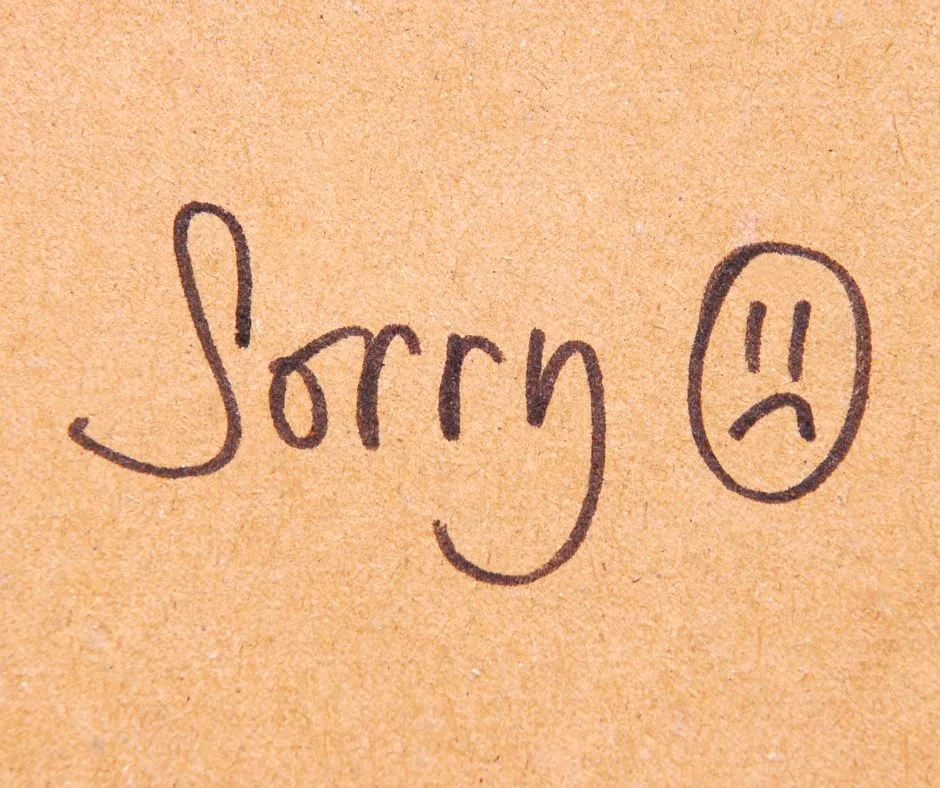日常の生活で「ありがとう」と言っていいところを、つい「すみません」と言ってしまうこと、ありませんか?
混んでいる電車内でスペースを譲ってくれる人がいたり
職場の上司から旅先のお土産をもらったり。
深爪で缶ジュースの蓋が開けられずに困ってるとき
隣の人が自分の作業を止めて開けてくれたような場面。
荷物を抱えてドアを通るとき
ドアが閉まってしまわないようドアを押さえて待ってくれたような場面。
そのように誰かに何らかの気づかいを受けたり
お世話になった場面を思い返すと、僕は
1.「ありがとう」だけ
2.「すみません」だけ
3.「すみません」プラス「ありがとう」
という3つのパターンを口に出していることに気づきました。
その中で自分でもずっと不思議だったこと。
それは、どうして「すみません」という「謝罪の言葉」が口から出てしまうのかということです。
相手が僕のために時間やお金、空間、気づかいを提供してくれた。
そこで僕は相手に何らかの負担や手間、迷惑をかけてしまった。
だから「すみません」が出てくるのかなと考えていたのですが・・・
その「すみません」のウラに隠された心のメカニズムを、もう一段深いところから解説してくれたのが
『菊と刀』(ルース・ベネディクト著)
です。
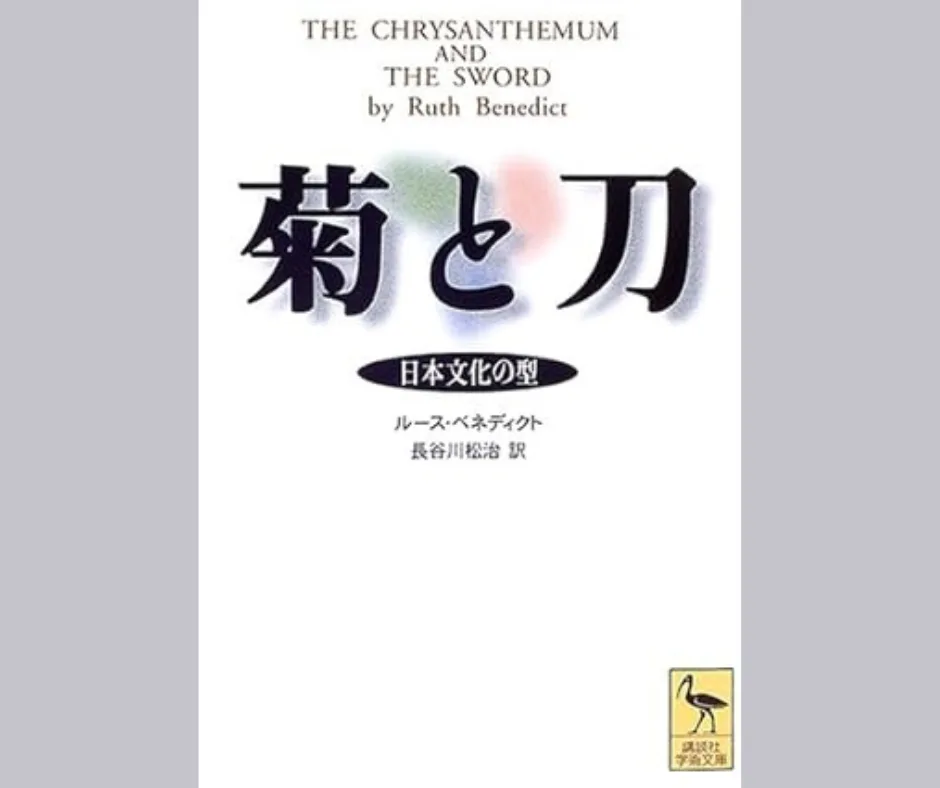
『菊と刀』は文化人類学者ベネディクトが第二次世界大戦中にアメリカ政府から依頼を受け、日本人の文化・行動パターンを解明するために書かれたものです。
当時、アメリカは日本軍人の捕虜が降伏しない姿から「この国民をどう屈服させられるか」という疑念を抱き、日本人の心理や文化を理解する必要があったとされています。
この著作が素晴らしいのは、著者ベネディクト自身が持っている価値観「差異を認めながらも安全が確保されている世界」で貫かれているところです。
この本には日本人の性質がアメリカやほかの何かと比べて「劣っている」と論じているような文脈が微塵もありません。
また「普通の人たち」に焦点を当て、ごくありふれた場面を「普通の日本人」がどう捉え、何を思考しているかを一貫して解説している点も素晴らしいです。
ところで「すみません」がなぜ口から出てしまうのか。
『菊と刀』では「恩」という言葉を使って解説しています。
「恩」とはお世話になった人からの「借り」のこと。
「恩」という「借り」は返さなければならないもの。
誰かに気をつかってもらったり、お世話になったとき
その受け取った「恩」を今すぐに返せなくて心苦しい。
見ず知らずの通りすがりの人が相手であれば
受けた「恩」を返す機会も今後ないだろう。
そんなときに口をついて出てくるのが
「すみません」という謝罪表現だということです。
著者ベネディクトは『菊と刀』を執筆するにあたって日本に行くことはできず
戦時中の制約の中で文献や日系人へのインタビュー、日本人捕虜の尋問調書、ラジオや映画、小説など膨大な資料のみを駆使して調査を行ったそうです。
日本に行かずとも、これだけ本質を突いた日本人の姿を描いているところに驚嘆します。
ところである調査文献(*)で
最近は誰かから気遣いやお世話になった場面では
「すみません」より「ありがとう」
を使うケースが多いとのことですが、あなたの周りではいかがでしょうか。
(*) 飯尾牧子著/感謝を表す表現:「ありがとう」と「すみません」