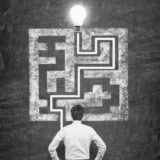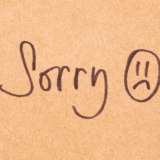お店でステーキを注文するとき、「ミディアム・レアで!」とお願いしても、いざ食べようとカットしてみると「ちょっとウェルダン」になってしまっていることがあります。
せっかくのステーキが僕のイメージする「ミディアム・レア」になっていない・・・こんなに悲しいことはありません。
以前、フランスでステーキ屋さんに入ったときも同じようなことがあり文句を言ったことがあります。
「ミディアム」になってしまっているステーキの断面を見せながら
「これ、僕がお願いしたミディアム・レアじゃないですよね?」と。
するとステーキを運んできたおばさんが
「いえいえ、このピンクの度合がミディアム・レアです!」と。
そこで再度言い返してもよかったのかもしれませんが、言い争うのは面倒くさいので
「メルシー(ありがとう)」と言って泣く泣く「ミディアム」で固くなっちゃっているステーキをいただきました。
海外の方と仕事していても、言葉や単語に対するイメージ、意味合いが異なることがよくあります。
例えば以前、教育関係の話をしているときに「カリキュラム Curriculum」という言葉が出てきました。
「カリキュラム」とは指導要領や指導計画のことで、何にどのぐらいの時間をかけ、どう教えるかを示したもの、というのが僕のイメージでした。
ところがそのイメージである国の教育関係者と話をしていると、どうにも嚙み合わないのです。
相手の方は「カリキュラム」という言葉を使いながら、ページ数や挿絵の分量、各章に宿題をどのぐらいつけるかといった話をしてくるので、僕の中で「教科書」のイメージが浮かび上がってくるのです。
それで
「あなたはさっきから教科書『Textbook』の話をしているの?」
と聞いたところ、相手はキョトンとした顔で
「いやいや、私たちはカリキュラム(Curriculum) の話をしているんだ」
と。
そこでわかったのは、その国では「教科書」のことを「カリキュラム」と言い、そもそも『教科書 Textbook』という単語を使わないのだということです。
また別のところでは、わりと大きめの備品を片付けるのに
「コンテナ(Container)に入れておいて」
と言われました。
僕は海上輸送でよく見かける大きなコンテナをイメージしてしまい、そんなコンテナが敷地内のどこにあったっけ?と戸惑ってしまったのですが、
相手の言いたかった「コンテナ」とは、倉庫に置いてある大きめの「プラスチックの箱」のことで、そのイメージの違いにびっくりさせられました。
ひどいものになると、英語の「明日(tomorrow)」を「将来、いつか」という意味合いで使うところもありました。
そんなことを知らなかった僕は、翌日になって「あれ、できた?」と聞きにいったとき、
相手は僕が一体何のことを言っているのかが理解できていなくて愕然とさせられました。
いつも無意識に使っている言葉や単語、言い回し・・・
海外の方との仕事では、そんなところに誤解や意識のズレといった落とし穴が潜んでいることがあります。
ある言葉や単語に対してイメージや意味合いが異なることで
ひどい場合は作業の段取りがおかしくなってしまったり
望ましい結果のイメージが合ってなくて取り返しがつかなくなることもありました。
最近、多国籍チームでいろんな機材を使った、ちょっと複雑な作業を行うことになったのですが
全員がそれぞれの機材や手順について同じイメージで話せているか
お互い英語を使っているけど、それぞれの単語の意味するところは皆同じになっているか
ウザがられたとしても「やっぱり今度ひとつひとつ確認しておこう」とステーキを焼きながら考えていました。
ステーキ 🥩・・・やっぱり自分で焼いて食べるのが一番ですね!
これぞ僕のイメージにピッタリの「ミディアム・レア」のビーフステーキが完成しました ✨
ウッシッシ・・・で今日もワサビ醤油と山盛りご飯でいただきます。
👉 無料相談・無料メンターサービスはじめました 👈
海外の方との仕事・コミュニケーション・チーム作りでお悩みの方へ
詳細はこちらから→ https://bit.ly/3Hupapd